
知られざる「モノづくり」の世界に迫るモノづくり探訪記。今回はスニーカーブランド「Bluestone」を訪問。Bluestoneは天然本藍染革と井原産セルビッチデニムというこだわりの国産素材を使い、すべて職人の手作りで製品を生み出している。その根底にあるのは、経年変化を楽しみつつ、リペアしながら長く使い続ける、ものを大切にする精神だ。
ここでは「100年スニーカー」のコンセプトのもとに作られた、「スクモレザー スニーカー」と「デニム×スクモレザー スニーカー」という2種類のスニーカーから、Bluestoneの魅力を発掘してみたい。
2020年1月27日
●取材・構成:編集部 ●文:大澤裕司 ●撮影:下山剛志[ALFA STUDIO]
こだわりの国産天然素材で作られた「100年スニーカー」
●自然な風合いが目を引く「スクモレザー スニーカー」
商品名のスクモレザーとは、アッパー(表革)に使われている天然本藍染革のこと。留紺(とめこん)、縹(はなだ)、藍の3色をラインナップ。自然な風合いが何よりも目を引く。
デザインはベーシックで、コンバースの「オールスター」に近い。飽きが来ず長く履けるデザインだ。重いコートを着る冬に履いても足元が華奢に見えないよう、つま先にボリューム感を持たせている。

新品も美しい発色だが、気になるのは藍染されたスクモレザーの経年変化の様子だ。Bluestoneデザイナーの赤理浩一さんが4年ほど履いたものを拝見したが、新品と比べると藍染の「青」がより際立ってきている。また、手で触ることで得られる皮脂で、ツヤが増しているのが分かる。
足が触れる中底と裏革には牛ヌメ革を使用しており、こちらはまた、スクモレザーとは違った色の変化が見られる。使うにつれて抜けるような青色に変化していく表革に対して、裏側は深みを増し、いわゆる「飴色」の状態に近づいていくのだ。

●デニムとレザーが融合した「セルビッチデニム×スクモレザー スニーカー」
こちらは、「スクモレザー スニーカー」のデザインはそのままに、アッパーの一部にデニム生地を使ったタイプ。革の色が異なる、留紺と縹の2色がラインナップされている。
使われているデニム生地は、セルビッチデニムと呼ばれるもの。ごく少量しか生産されていない上に扱いが難しい素材だが、やさしい風合いが魅力的である。使い込むとブラックに近い紺色から青色に近い色合いに変化。タテ落ちが進んでいくのもデニムならではだ。独特の経年変化が楽しめるところはスクモレザーと同じといってもいい。


こだわり抜いた天然素材でスニーカーを作る
スクモレザーもセルビッチデニムも、赤理さんが職人のもとを訪ねて現物を目にし、魅せられた素材である。スクモレザーは、徳島県産の阿波藍を繰り返し乾燥・熟成・発酵させてつくった天然染料「蒅(すくも)」で本革を染色したもの。色合いもさることながら厚くて柔らかいという革の特性に惹かれ、自らのスニーカーに取り入れることを熱望した。

ただ、スクモレザーは非常に柔らかく成形が難しい。「スクモレザー スニーカー」では、表革と同じ厚さの牛ヌメ革を裏革として使用することで、やわらかいがしっかりとした履き心地を作り上げている。
さらに、裁断しにくいのもスクモレザーの難しいところ。普通の革は染め上がった後、見栄えを良くするために顔料染めなどの表面加工を施すが、スクモレザーは染色後、何も手を加えてない。小さなキズや血筋が残っているので、パーツを切り出すときには、革を引っ張りながら小さなキズを見つけ、それを避けるように裁断を行っている。
一方、セルビッチデニムは、岡山県井原市でごく少量だけ生産されているデニム生地。撚りの弱い糸を使って特殊な機械で織られており、完成までに半年ほどの時間を要する。

セルビッチデニムは防縮加工や斜行止め加工をせずに仕上げた素材で、手で広げるとすぐにクルリと丸まってしまう。シューズには使いづらいが、撚りの弱い糸ならではの風合いの美しさに惹かれたこと、革と同じで経年変化が楽しめることから、赤理さんはシューズに活用したいと望んだ。
最初に工房にオファーしたときは、時間がかかる上に少量しか生産していないからと断られたが、諦めずにお願いし続けたところ、「半年待ちになるけれど……」と言って提供してもらえることになったそうだ。
「スクモレザースニーカー」の履き心地は?
さて、赤理さんがその目で確かめ、惚れ込んだ素材で作ったスニーカーの履き心地はどうなのか? 気になるところだ。ご好意で「スクモレザー スニーカー」を試し履きさせてもらうことができたので、その感想をお伝えしたい。
履いた第一印象をひとことで言うと「軽い」。レザースニーカーは重い印象がある上に「スクモレザー スニーカー」はつま先にボリューム感があるので、履いて歩くと重く感じると予想していたが、実際はその正反対。スクモレザーの柔らかさも起因しているのだろう。
何よりも驚いたのが内側だ。アッパー裏に1.6mmと厚めの牛ヌメ革を使っているにもかかわらず柔らかく、足へのフィット感が絶妙。吸い付いている感じが心地よい。スニーカーでは珍しい竹シャンクが入っているので、履いた時の安定性が高い。普通のスニーカーでは感じられない芯が実感できるが違和感はなかった。
ショップ内を少し歩いただけだが、軽くて柔らかいので、歩いているときのストレスはほぼ皆無。ファッション性と実用性の両方を兼ね備えていることが実感できた。
靴以外のアイテムも積極的に作っていく
このような扱いが難しい素材を、Bluestoneでは財布やシューホーン(靴べら)といったアクセサリー類にも活用している。百年スニーカー以外にもさまざまなラインナップを増やしている理由を赤理さんに尋ねると、次のように答えてくれた。
「スニーカーは長く愛用してもらえるものを作りたいので、定番の型以外は作らないことにしています。でもBluestoneの魅力を知ってもらうためには、別のアイテムも必要だと考えました。財布はそのために作ったもの。
お客様それぞれが求めるものを通してBluestoneというブランドを知ってもらえればよいので、靴以外のものもこれからもどんどん作っていきたいです」


●パッケージにも込められたリユースの精神
スクモレザーやセルビッチデニム以外にも、Bluestoneの製品では天然素材が活用されているが、天然素材でモノづくりをするのはリペアとリユースをしやすくするためでもある。
そのリユースの精神は製品以外のパッケージにも及んでいた。ユニークなのがスニーカーを買った時についてくる靴箱。片足ずつ四角い紙筒に収め、倉敷市産の帆布でできた袋に入れている。
紙筒が不要になり捨てたら、残った袋をクラッチバッグとして使うことができるのだ。「靴箱は作るのに結構お金がかかりますが、捨てられることがほとんど。せっかく作ったのにもったいないので、簡単に捨てられず長く使えそうなものを作りました」と赤理さん。購入者にはうれしいサービスだ。



シューホーンのパッケージも凝っている。八角柱のグラスボトルを採用した。ギフトとして購入されることもあることから、思い出に残るものとしてグラスボトルを選んだ。

リユースの精神は、東京・日本橋にあるBluestoneのショップづくりにも生きている。ショップは倉庫を改装して作られたものだが、廃材をキレイに磨いたりリメイクしたオブジェが飾られており、とてもお洒落な雰囲気だ。

親から子へ受け継がれる、100年スニーカーへ
スニーカーは履き潰して買い換えるのが当たり前。そんな思い込みや固定観念の対極に位置するのがBluestoneのスニーカーだ。「100年スニーカー」というコンセプトを掲げるのも、リペアしながら履き続け、子や孫に受け継いでもらいたいという想いがあるためである。国産の天然素材にこだわったのも、飽きの来ない定番デザインを採用したのも、長く受け継いでもらいたいからだ。
リペアはスニーカーを作ってきた職人達自らが担当する。「100年スニーカー」実現のために、ベテランの靴職人の指導のもと30歳代を中心とした若い職人たちが育っており、製造、メンテナンスともに、当面は心配ないのも強みだそうだ。
たくさんの職人達の手を渡って作られてきたBluestoneのスニーカーを手に、親子でそのストーリーを感じ取ってみるのもいいかもしれない。

「Bluestone」
https://www.blue-stone.jp/
靴と鞄を企画・製造・販売・輸入する興和インターナショナルが2014年に立ち上げたオリジナルブランド。レザースニーカーをはじめとした革製品を、職人が手作りによって提供する。東京・日本橋にショップを構える。






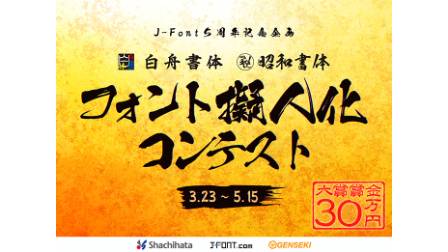











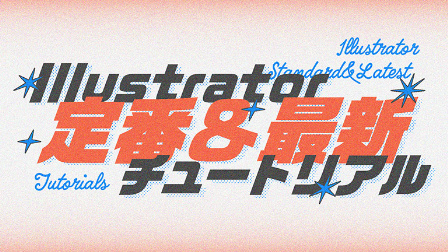














2020.01.27 Mon