
新型コロナウイルス禍によって、IT企業も多大な影響を受けて命運が分かれているが、その中でAppleは、巧みな舵取りによってダメージを最小限に留めることに成功したといえるだろう。
それは、前回のiPhone SEの記事でも触れたように、サブスクリプションサービスからの安定した利益が得られることと、世界経済の停滞を予期したものではなかったが、タイムリーかつブランド力を落とさずに廉価版iPhone(=SE)を市場投入できたことによるところが大きい。
その流れに乗って発表された新型MacBook Proは、噂されていた14インチではなく13インチモデルのまま、基本デザインも変更せずに登場した。この筐体と仕様構成には、やはりこの時期ならではの深謀遠慮が感じられる。そのあたりの分析も含めて、プロユースに適した仕様がどれかを考えてみたい。
14インチモデルは存在したのか?
筆者もその1人だが、読者の皆さんの中には14インチモデルの登場に期待していた方がおられるかもしれない。そこでまず、その点について触れておこう。あくまでも筆者の私見だが、ここを押さえておくことで、今回の新13インチモデルの仕様ラインアップに対する納得度が高まるからである。
結論からいえば、おそらく14インチモデルのプロトタイプは存在し、今回のタイミングで発表することを考慮していた可能性も十分あったと考える。
というのは、エントリーモデルのMacBook Airもスクリーンサイズが13インチのみとなり、最新モデルではRetinaディスプレイも環境光に応じて色合いが自動調整されるTrueTone仕様(ただし、MacBook ProやiPad Proのような広色域P3対応ではなく、sRGB対応)に変更され、以前と比べてMacBook Proの13インチモデルとの差が詰まってきていたことが1つ。
加えて、iPad ProもiPad OSのアップデートやフローティングスタイルのMagic Keyboadの登場によって、よりMacBook系に近い操作が可能となったため、こちらの12.9インチモデルも含めると、ほぼ同じ画面サイズの製品が3種類存在する状態が生じていたことも指摘しておきたい。
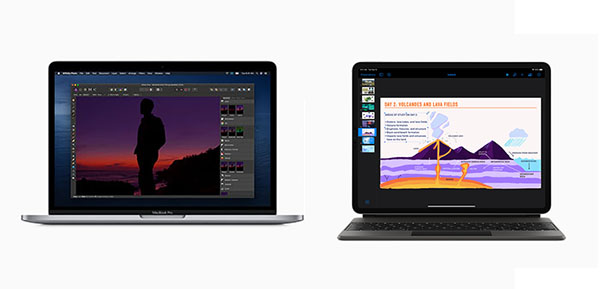
もちろん、それぞれの製品が完全に競合しているわけではなく、性格付けも異なっている。その違いは知識のある人間から見れば明白かもしれないが、Apple全体の製品数が増える中で、一般消費者に向けたマーケティング上のメッセージを鮮明に打ち出すためにも、より明確な差別化が求められていた。
その意味では、MacBook Proの上位モデルがかつての15インチではなく16インチとなっている今、13インチモデルを14インチに格上げし、それより小さなスクリーンサイズは、MacBook AirとiPad Proに任せたほうが、販売戦略上も有利と思われる。
堅実性を重んじた新13インチラインアップ
では、14インチモデルの計画があるとして、なぜ今回それを見送ったかといえば、やはり昨今の世界経済の状況を鑑みてのことだろう。14インチモデルは、Apple本来の高付加価値路線に属するはずで、全体的には13インチモデルよりも価格帯が上になる公算が強い。しかし、サプライチェーンや生産立ち上げに伴う障壁も少なくて済むと考えられる13インチ筐体のままでアップデートを行うほうが、地球全体が新型コロナウイルス禍にあるこのタイミングでは安全だ。
それも、準備期間などを考慮すると、ここ1、2ヶ月の間の話ではなく、遅くとも今年の頭にはそうする決定が下されていたと考えられよう。たとえば、台湾は昨年12月末の時点でWHOに対して、武漢における非定型肺炎の発生を知らせる文書を送っており、幅広いネットワークを持つAppleがそれに類した情報を握っていた可能性は十分ある。
その上で、Appleが重要視したのは、13インチモデルの枠内で、iPhoneにおけるSE的な買いやすい仕様と、MacBook Proに相応しいハイパフォーマンス仕様をカバーすることだった。
具体的には、新MacBook Pro 13インチモデルの下位仕様(1.4GHzクアッドコアIntel Core i5プロセッサ、8GB 2,133MHz LPDDR3メモリ、256GBストレージ)は、MacBook Airの上位モデル(1.1GHzクアッドコアCore i5プロセッサ、8GB 3,733MHz LPDDR4Xメモリ、512GBストレージ)と同一価格(税別134,800円)であり、ストレージを512GBにアップしても2万円高で済む。
一方で、上位仕様(2.0GHzクアッドコアIntel Core i5プロセッサ、16GB 3,733MHz LPDDR4Xメモリ、512GBストレージ)は税別188,800円(1Tストレージでは、同208,800円)となるが、格段に高速なプロセッサとメモリ、そして、4基のThunderbolt 3ポート(下位仕様では2基)が手に入る。
プロが注目すべきはアーキテクチャの世代
このあたりの仕様の違いを、公式サイトの説明図も利用しつつわかりやすくまとめてみた。赤い部分は旧世代あるいは下位の仕様であり、青い部分が最新ないしは上位の仕様となる。
ここで注目すべきは、プロセッサの世代とメモリの帯域、そして、Thunderbolt 3のポート数である。また、かつては、CPUのクロック数とコア数が優劣の目安になった時代もあったが、近年は、熱設計も性能向上に重要な役割を果たすようになり、TDP(熱設計電力=最大放熱量)が大きくないと、発熱の大きな高負荷・高クロック状態を長く維持することができないため、その点に留意することも必要だ。
新MacBook Pro 13インチの下位モデルの仕様は、基本的に従来モデルをほぼそのまま踏襲している。異なるのは、不評だったバタフライキーボードをシザー式のMagic Keyboardに置き換え、さらにEscキーをTouch Barから独立した物理キーに割り当てて使い勝手が向上した点にある。
もちろん、価格が抑えられたことで魅力が増したこの下位モデルは、第8世代(開発コードネーム:Coffee Lake)とはいえTDPが15Wのプロセッサを搭載しており、同じ4コアでもTDPが10Wの第10世代プロセッサを搭載するMacBook Airの1.5倍以上(マルチコア利用時)のパフォーマンスを発揮できる。そのため、たとえば昨今のテレワーク用に少し高性能なノートMacが欲しいといったニーズには最適の1台といえる。
しかし、プロのクリエーターが選ぶとすれば、最新アーキテクチャを採用し、高度なビデオ編集や3Dレンダリングなどの高付加な処理を余裕を持ってこなせる上位モデルを選択すべきである。この場合、第10世代プロセッサの中でも、TDPが28Wのものを採用して余裕ある熱対策が採られている。そのため、下位モデルとの比較でシングルコア使用時でも約1.3倍、マルチコア使用時では1.4倍弱のパフォーマンスを発揮できる。
この上位機種で採用されているIce Lakeプロセッサは、特に純正のコンピュータグラフィックスAPIであるMetalへの最適化が進んでおり、GPUの負荷が高い処理では下位モデルの1.5倍程度のパフォーマンスを発揮するため、一説にはIntelがAppleの要望に応じてカスタマイズした専用品ともいわれている。
Thunderbolt 3ポートが4基あることも含めて、これらのパフォーマンス差を考えるならば、プロの選択肢は上位モデル一択といってよい。価格差も十分納得できるものであり、内容を考えれば安いとさえいえるかもしれない。
今後の新13インチモデルの売れ行きやウイルス動向の影響は受けるだろうが、14インチモデルも近い将来(今秋~来春)には登場することが予想される。その場合、内部空間の余裕を活かし、現在はプロセッサ統合型のGPUを独立させて、さらなる高性能化を図ることも考えられよう。今回の13インチモデルも十分に魅力的だが、急ぎでなければ、それまで待つのも1つの選択肢といえる。
逆に、若干でも大型化する14インチモデルは可搬性の点では13インチに劣ることになる。したがって、持ち運ぶ機会が多いユーザーであれば、十分な買い得感のある今回の上位モデルを前向きに選択するという判断もできるだろう。



















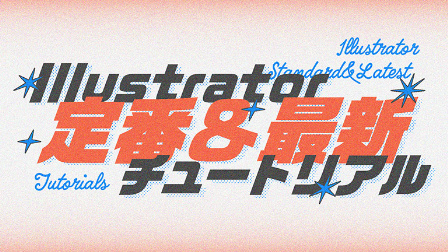

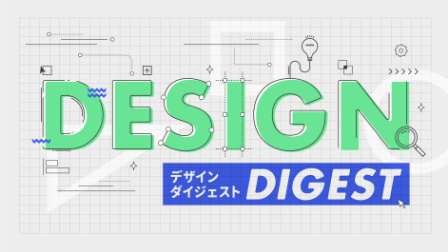












2020.05.18 Mon