
知られざる「モノづくり」の世界に迫る本連載。第一回目は、時間の経過とともに表情を変え、唯一無二の「モノ」として、根強い人気を誇る革製品に注目! もしかしたら一生ものとして愛用するかもしれない、そんな革製品の魅力や奥深さとは?
訪れたのは都内にショップ兼工房を構える革鞄工房「analogico」(アナロジコ)。良質の革製品が生まれる秘密と、モノづくりのクリエイティブについて、アナロジコ代表・鞄職人の末吉隼人氏に伺った。
2019年7月26日
●取材・構成:編集部 ●文:渡辺まりか、編集部 ●撮影:鈴木隆志[P-throb]
「革」から生まれるインスピレーション
アナロジコは、工房と店舗が一体となった素敵な空間のアトリエショップ。お店を訪れた人は、職人たちが革製品を作り出すその瞬間を間近で見ながら、製品を購入できる。


アナロジコではすべての工程を職人の手作業で行う。徹底したアナログのモノづくりと、革の良さを最大限に生かす素材へのこだわりによって、革本来の魅力が溢れる製品を日々生み出している。


革製品は素材の特性が重要なポイント
革製品では、素材の特性がそのままビジュアルや使用感に関わるため、作り手はもちろん、購入者は自分好みの製品を選ぶ際に大きなポイントとなる。アナロジコの製品のほとんどに使われているのは、イタリアのタンナー(製革業者)、La Perla Azzurra(ラ・ペルラ・アッズーラ)社のMissouri(ミッスーリ)という、ナチュラルな風合いが特徴の貴重な革素材だ。「この革を使って、自分だけの製品を作りたいと思ったのが、自分の工房を立ち上げるきっかけでした」と末吉氏は語る。(※革素材の詳しい解説はこちら)
La Perla Azzurra社の革に出合って作りたいという欲求に駆られたように、今も末吉氏の「作りたい」は革素材からはじまっている。デザインの構想に合う革を探すのではなく、革からインスピレーションを得て、その革素材が引き立つものを作るという。
こうした天然にこだわったナチュラルレザーは、色ムラがあったり、傷がつきやすい面もあるが、それも風合いの一つになる。アトリエショップを訪れる常連客たちも、そんな生き生きとした革の魅力に惹かれて購入していくようだ。

革素材は、部位によって繊維の密度が異なり、それによって生まれるシボ(革の表面の凹凸模様)の表情も変わる。アナロジコで使うのは、牛の首から腰の部分にあたる「ショルダー」部位のみ。繊維密度が低く伸びてしまいがちな腹部は使わない。「値段が高くても、良い部位だけを使いたい」と末吉氏。日本だと、背骨のところで左右に分けた「半裁」しか手に入らないので、部位別に売っているイタリアのMissouriはこうした面においても理想的なのだ。
自然な風合いを生かしたカラードレザー
アナロジコには、カラードレザーを使ったアイテムもあるが、こちらも革本来の風合いが残っている。その理由は、「トップ」と呼ばれる色調整用の仕上げを施していないから。

一般的なカラードレザーは下染めの後、表面に染料を吹き付けて色を均一に整えるため風合いが出づらいが、アナロジコでは自然な風合いを残すため、下染めのみで仕上げた革素材を使っている。
また、天然の素材だけでなめす※1、タンニンなめし※2の革を使うのもアナロジコのこだわり。流通量の大半を占めるクロムなめし※3の革は、扱いやすく、品質も均一に保てるが、革本来の表情を楽しむならタンニンなめしの革が一番だという。特にトップを吹き付けていないタンニンなめしの革には、革の持つ自然な表情がそのまま表れるからだ。
※1 なめす:動物の皮を薬品などで処理して、長い間腐敗せず柔軟性を保つ状態にすること
※2 タンニンなめし:植物由来のタンニン(渋)を使ってなめしした革
※3 クロムなめし:化学薬品を使ってなめした革。現在流通する革製品のほとんどがこのクロムなめし
そんなタンニンなめしは「刻印」の焼きも美しく表現する。「タンニンなめしだと刻印もきれいに入ります。これもタンニンなめしの革を気に入っている理由の一つですね」(末吉氏)


職人が手作業で作り上げるアナロジコの革製品づくり
アナロジコの製品は、すべて職人の手作業によって生まれるが、今回はなんと貴重な制作工程、①裁断 ②コバ磨き ③革漉き~糊付け~縫製 ④ひっくり返し ⑤整形、をその場で一から実演して頂いた。革の風合いの良さや、手作業の温かみはどんな過程を踏まえれば表現できるのか? さっそく紹介していこう。
①裁断


はじめに行うのは、裁断。これは、革の上に製品のパーツとなる型紙を置き、それに合わせて切り分けていく作業なのだが、実はこれが最も気を遣うポイント。
「革には繊維の方向があって、部位によって密度も異なるので、完成品をイメージして、それぞれのパーツごとに最も合う部位を無駄なく切り出さなければなりません。目に付きやすいメインパーツにはきれいなシボの出る場所を当てるといったように。
また、革の繊維の読みを間違えると、使用しているうちに不必要に伸びてしまいます。トートバッグなどでは、口の部分が伸びてしまったらみっともないですよね。そうならないように、計算して裁断するのが難しいんです」(末吉氏)
②コバ磨き

パーツを切り出したら、次はコバ磨き。「コバ」とは革の裁断面のこと。裁断したままでは手で触った時に皮革繊維がボソボソと毛羽立ってきてしまうし、エッジが立ち過ぎるため手触りも良くない。そこで磨いて艶を出すコバ磨きを行う。切りっぱなしのものと比べると、磨き上げたコバには高級感が漂う。切り出したパーツ1枚1枚、全て手作業でこれを行っていくのがアナロジコ流。
③革漉き~糊付け~縫製
裁断、コバ磨きの工程を経たら、次は形にしていく作業に進む。まずは革漉き(かわすき)。これは厚みのあるMissouri革の裏側を削いで、薄くする作業だ。縫い合わせたときに厚みが出すぎないよう、また折り曲げた際に立体感が出るようにするもの。
革漉きの次はラバーで糊付けをする。いわゆる「仮縫い」のような工程だ。その後、専用のミシンを使って縫製を行う。


④ひっくり返し

トートバッグ、リュックサックなど袋物のほとんどは革の表面を内側にした状態で縫製するため、裏表をひっくり返す作業が必要になる。Missouri革は厚みがあり、タンニンなめし特有のコシもあるため、かなり力を入れなければならない。 作業によっては革に亀裂が入ることも。力を加減しながら丁寧に裏返していく。
⑤整形



ひっくり返しの後、さらに細かく形を整える整形作業を行う。これですべての工程が完了だ。アナロジコの製品は、一つ一つこうした手順によって丁寧に作り出されている。
定番製品でも、常に「改良」は怠らない
製品が完成してもそれで終わりではない。アナロジコでは、製品づくりの一環として欠かせないのが「改良」。例えば、人気の定番商品である『L字ファスナー財布』も、半年ほど前に改良を施したという。
「このままでも使いやすいのですが、外縫いにして、マチを付けたらもっと使いやすいのではないかと思い立って、試しに作ってみたんです。すると小銭がたくさん入り取り出しやすい。定番商品はこちらに切り替えました。一度定番になった商品を変えるのは、Web上の掲載写真を変えたりしないといけないので大変なのですが、より良いことに気づいてしまったら、もうやるしかないんですよね」(末吉氏)

長く使うほど味が出る、革製品の奥深さ
最後に、アナロジコのモノづくりのコンセプトから、革製品の奥深い世界を紹介しよう。アナロジコの製品のモットーは「長く使えること」だと末吉氏は言う。そのためには、「丈夫であること」と「時代の流れに左右されないデザインであること」という2つの要素が絡んでくる。末吉氏が使っているMissouriは、厚みがあり長く使える革素材。そして、タンニンなめしなので、クロムなめしでは味わえない飴色への変化(エイジング)も楽しめる。
縫製の時に使う糸にも意味がある。末吉氏が工房で使うのは、0番手から1番手という極太の糸。アナログを名前の由来とする「アナロジコ」らしい温もりやクラフト感を見た目に添えるだけでなく、丈夫さも担保する。「細い糸は切れやすいですから。太い糸で縫うのは大変だけど、長く使えるようにするためには必要なことだと思うので、アナロジコでは主に0番手と1番手の糸を使っているんです」(末吉氏)
トートバッグやリュックに、革製品でよく目にする布などの裏地を付けないのも、長持ちさせるためだという。布は革より弱いので先に擦り切れてしまう。壊れやすい要素はできるだけ排除しているのだ。
流行に左右されないシンプルな造形もそうした思いの表れ。いっときは装飾に惹かれても、それに飽きてしまったら使わなくなる。古着屋で魅力を放つ鞄のような、この先もずっと使えるデザイン。「私が作るものは全部、四角と三角と丸という普遍的な形で出来ています。装飾面で自分の個性を入れてしまうと、飽きてしまうので、使う人の一部になるようなデザインを心がけています」(末吉氏)

新しい「革」への挑戦
今、アナロジコの店内にはこれまでと少し異なる、まるで雪が降り積もったかのような白いテクスチャーの皮革製品を見ることができる。
この新たなシリーズは、La Perla Azzurra社がイギリスのブライドルレザーという革の製法を取り入れて製革した『アラスカ』という革素材を使ったもの。定番のMissouriにワックスをたっぷりとかけて白くしており、使い込むうちにワックスが溶けて革に染み込み、その後は通常のMissouriのように飴色に変化するという、3段階の革の表情を楽しめる製品だ。

求めていた最高の革素材Missouriに出合った後でもなお新しい出合いを求め続ける末吉氏。これまでも多くの職人達を虜にしてきたであろう「革」という素材には、底知れぬ魅力と可能性が詰まっているようである。

終わりに、革のプロである末吉氏に皮革製品のお手入れのコツを聞いてみた。基本的にはアナロジコで扱っているタンニンなめしの革素材を使ったものが対象となるお手入れ方法だが、お手持ちのアイテムにも当てはまるものがあるかもしれないので、参考にして欲しい。
皮革製品を長持ちさせるのに欠かせないお手入れのコツとは?
デイリー:使い終わったら乾拭きをして埃や油脂などを落とす。何かの拍子に付いた汚れや、角の黒ずみなどは柔らかい消しゴムで消すとよい。その際、力を入れすぎると革が白っぽくなるので注意する
スペシャル:3カ月に一度ほどの割合で皮革用オイルを塗り込む。必ず乾拭きした後の乾いた状態で、布にとったオイルを少量はたくように付けてからなじませるように塗るのがコツだ
エマージェンシー:雨などで濡れてしまった場合は、できるだけ速やかに水を拭き取る。拭き取りが遅れて、水シミができてしまった場合は、周りも濡らしてスポットの水ジミが目立たないように。よく乾燥させたら、ワックスを塗り込む
 analogico
analogico
https://analogico.jp/
代表の末吉隼人氏の叔母が使っていたという代々木のアトリエを受け継ぎオープンさせた、東京・代々木の革鞄工房。制作の全工程を一貫して手作業で行う「アナログな鞄づくり」にこだわり、革本来の自然な風合いを生かした製品づくりを行う。店舗販売のほか、定番商品はインターネットからも購入できる。






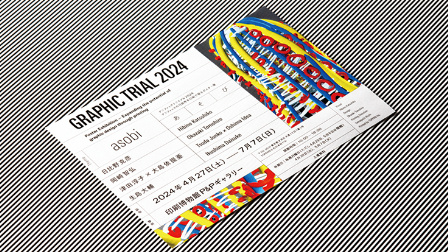


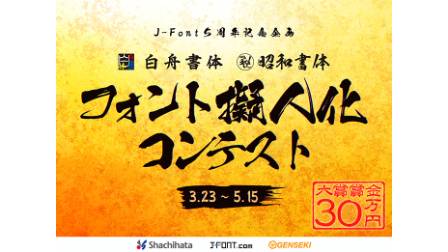


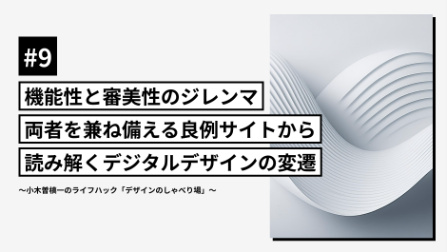




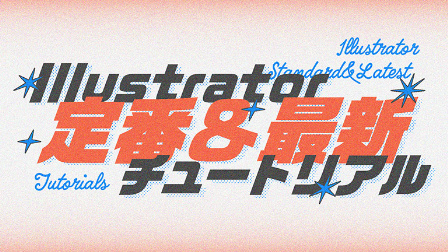















2019.07.26 Fri